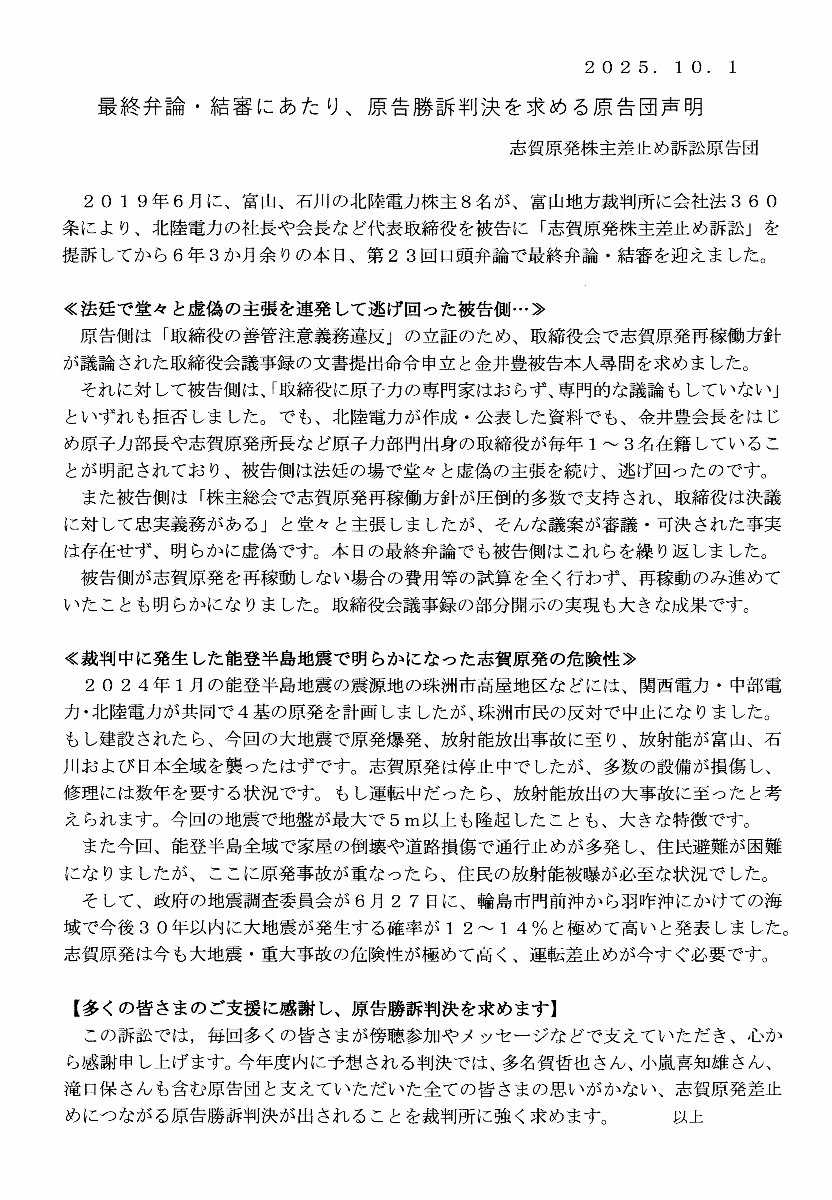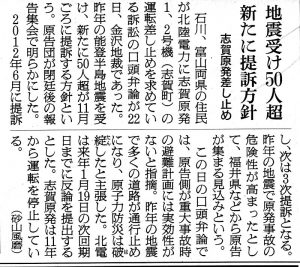11月17日、私たちの「志賀原発を廃炉に!訴訟」は新たな一歩を踏み出しました。
 このたび「第三次原告団」に加わった原告らは12時30分に兼六園下に集合、横断幕を掲げて金沢地裁まで行進しました。
このたび「第三次原告団」に加わった原告らは12時30分に兼六園下に集合、横断幕を掲げて金沢地裁まで行進しました。
そして満を持して金沢地裁に訴状を提出、その後金沢白鳥路ホテル山楽に会場を移して、第一次・第二次の原告やサポーター、弁護団とともに、報告集会・記者会見を行ないました。
この訴訟は2012年6月に原告120人で金沢地裁に提訴し、翌2013年に福島からの避難者5人を加えて第二次提訴を行い、現在までに46回の口頭弁論が行なわれています。私たちは毎回原告意見陳述を行い、さまざまな観点から志賀原発の危険性を訴えてきました。
しかしながら、提訴から13年が経過したにもかかわらず、未だに結審に至っておらず、裁判所は司法の独立を放棄したかのように、原子力規制委員会の判断を待ち続けるという姿勢に固執しています。
 報告集会の冒頭で北野原告団長はこの第三次訴訟のねらいを、原告団組織と運動の強化であると述べるとともに、昨年の能登半島地震でこの裁判の潮目が大きく変わったことを指摘しました。北野さんは新たな原告が、これまでの石川富山や福島からだけでなく、能登在住者や北陸三県、そして全国で原発訴訟をたたかう仲間の代表が加わったことも明らかにしました。
報告集会の冒頭で北野原告団長はこの第三次訴訟のねらいを、原告団組織と運動の強化であると述べるとともに、昨年の能登半島地震でこの裁判の潮目が大きく変わったことを指摘しました。北野さんは新たな原告が、これまでの石川富山や福島からだけでなく、能登在住者や北陸三県、そして全国で原発訴訟をたたかう仲間の代表が加わったことも明らかにしました。

 その後、新原告を代表して4人の方が決意を述べました。
その後、新原告を代表して4人の方が決意を述べました。
珠洲から新たに加わった若い落合さんは小学生のとき珠洲原発闘争を経験し、大人たちが真剣 にたたかっている姿を見ながら育ってきました。落合さんは昨年の能登半島地震の震源が珠洲原発予定地の高屋・寺家のすぐ近くだったことに触れ、もしあそこに建っていたら多分私たちは生きていないだろうし、陸路からも海路からも助けに来てもらえないことがよくわかったと語りました。そして、自分のもっと下の世代にもこの裁判に興味を持ってもらえるよう、原告の一員として活動していきたいと力強く決意を表明しました。
にたたかっている姿を見ながら育ってきました。落合さんは昨年の能登半島地震の震源が珠洲原発予定地の高屋・寺家のすぐ近くだったことに触れ、もしあそこに建っていたら多分私たちは生きていないだろうし、陸路からも海路からも助けに来てもらえないことがよくわかったと語りました。そして、自分のもっと下の世代にもこの裁判に興味を持ってもらえるよう、原告の一員として活動していきたいと力強く決意を表明しました。

左は朝日新聞(11/18)、右は北陸中日新聞(同)
※クリックすると拡大