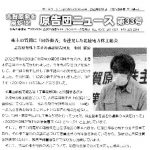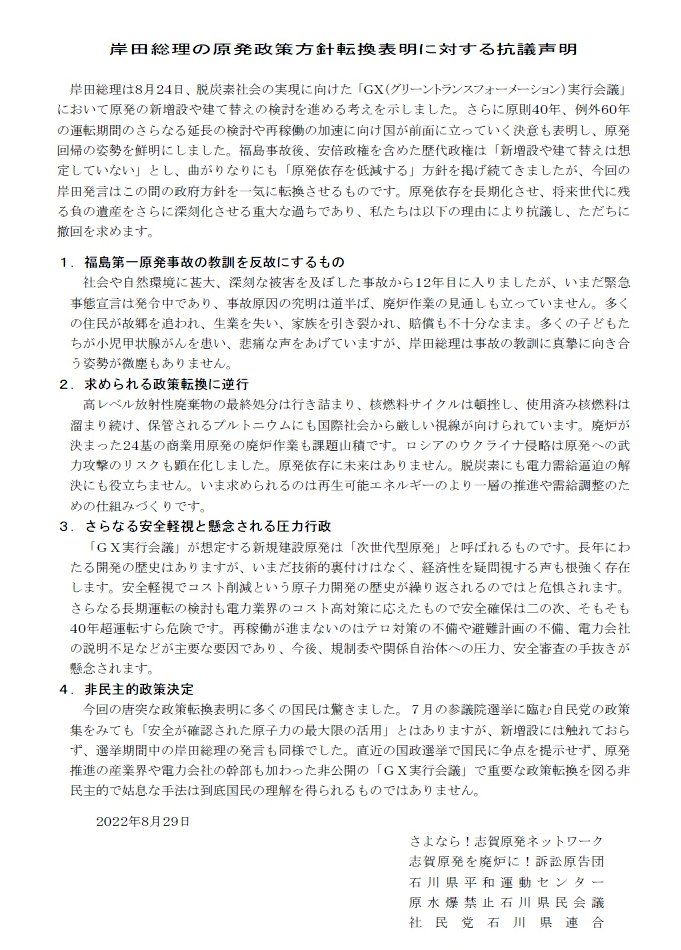志賀原発株主差止め訴訟(富山訴訟)の第11回口頭弁論が10月5日、富山地裁で行なわれました。裁判所近くに集まった原告・弁護団は、横断幕や原告団旗を掲げて裁判所まで行進しました。今回も傍聴抽選はなく、原告・サポーターは先着順に入場し、裁判は午後3時に開廷されました。
今回原告弁護団は3本の準備書面を提出しました。
 最初に坂本弁護士が第23準備書面「裁判所の見解について」をパワーポイントを使って要約陳述しました。
最初に坂本弁護士が第23準備書面「裁判所の見解について」をパワーポイントを使って要約陳述しました。
裁判所は前回(6月15日)の口頭弁論において、株主による差止請求権を行使するための要件である「回復することができない損害を生じるおそれ」がある場合(会社法360条3項)とは、「広範囲に放射性物質を飛散させる」ような会社の全資産(北陸電力の場合約1.5兆円)をもっても償えないような重大事故が発生した場合に限られる、と表明しました。
これに対して坂本弁護士は、裁判所の見解は賠償主体を会社(補助参加人)とする点においても、損害の規模・程度の点においても、差止請求権の内容をあまりにも狭めるものであって、従来の学説や裁判例と相容れない(=誤っている)と率直に指摘しました。仮に重大事故が起きなくても、志賀原発を再稼働する準備をするだけでも数十億円もの被害が発生するおそれがある。こうした経済面での被害も善管注意義務の対象になるはずだ、と主張したのです。
また第24準備書面「新規制基準の限界」では、新規制基準は「世界最高レベルの基準」でもないし、田中元規制委員長が何度も表明したように「それをクリアーしたから安全だというものでもない」から、新規制基準に則って再稼働したとしても重大事故が起きる可能性がある、という主張をしています。
また第25準備書面「志賀原発の経済性について」では、大島堅一龍谷大教授の意見書に基づいて、2023年度に再稼働するという(現実的にはあり得ない)北電に有利な想定に立ったとしても、発電コストは志賀2号機で11.8円/kWhとなり、どの電源よりも高くなるということを明らかにしました。
一方被告側は求釈明の回答をしたと称する準備書面(9)を提出しました。
法廷では「裁判所の見解に異論はない」と述べ、原告に対しては被告の準備書面などで反論済みであり、主張は出尽くしている。早期に裁判を終結すべきだとして、結審するよう求めました。
これに対して裁判所は自らの「見解」について正しいとも間違っているとも表明せず、「この点は今後の進行を踏まえた上で、必要に応じて検討する」とし、原告には被告の準備書面(9)に対する反論を、被告には原告第24準備書面に対する反論を、それぞれ次回弁論までに提出するよう求めて閉廷しました。
裁判終了後、原告や弁護団・支援者らは弁護士会館に移動し、報告集会を開催しました。

次回の裁判は2023年1月11日(水)、次々回は3月20日(月)いずれも午後3時から開かれます。