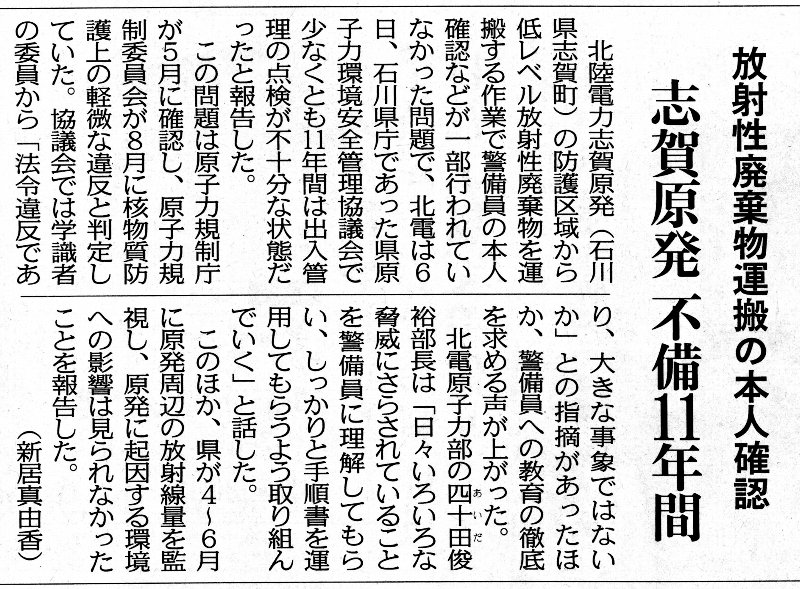11月24日、志賀原発での重大事故を想定した石川県原子力防災訓練が行なわれました。
防災計画では9割の住民が自家用車で避難することを想定していますが、昨年の能登半島地震では多くのクルマが倒壊した住宅の下敷きで壊れたり、津波で流されたりしました。しかも、多くの道路が崖崩れなどで寸断され、広域避難は不可能でした。また全壊家屋ではもちろん、半壊でも放射能を防ぐ効果は大きく低減し、どこにも逃げられない住民は被曝(ひばく)し続けることになります。

私たち原告団は石川県平和運動センターや社民党石川県連合など5団体とともに、監視行動やチラシ配布活動を行ない、終了後抗議声明(下記)を発表しました。
《抗 議 声 明》
石川県は本日午前7時から志賀原発の重大事故を想定した原子力防災訓練を実施した。目的は原子力災害時の緊急時対応に万全を期すために災害対応体制を検証することとされ、馳浩知事は原子力防災に対する住民の理解促進を図ることをテーマの一つとして掲げている。
志賀原発1号機稼働以降、私たちは原子力防災訓練に対して毎回監視行動に取り組み、抗議声明などを通じて訓練の課題や問題点を指摘してきた。奇しくも能登半島地震で住民は避難不可能、孤立し被ばくを強いられるという私たちの懸念は実証されることとなった。この間の原子力防災訓練は、大地震が起こり原発震災に至っても住民は無事避難できるという、志賀原発の再稼働を後押しするキャンペーンでしかなかったのである。能登半島地震を教訓とするならば、残された選択肢は志賀原発の廃炉しかない。
遺憾なことに昨年に続き今回も、過去の過ちを反省することなく訓練が繰り返された。能登半島地震を経験しながらも教訓化しないという意味で、これまで以上に悪質だと厳しく指摘しなければならない。以下、問題点を3点に絞って指摘し、怒りを込めて抗議する。
1.志賀原発の再稼働のための原子力防災訓練
地震の被害や原発事故の影響を過小評価し、あたかも被ばくを回避し避難できるかのような訓練を繰り返す理由は明白である。北陸電力が一日も早い志賀原発の再稼働を目指し、再稼働の条件の一つに「しっかりとした避難計画」の構築が求められているからである。
原発回帰に突き進む自民党政権は、菅政権以降「しっかりした避難計画がない限り、再稼働が実態として進むことはない」との答弁を維持している。「しっかりした避難計画」とは、被ばく容認の原子力災害対策指針に沿った「緊急時対応の取りまとめ」を意味している。だからこそ各地で住民の被ばくを回避しないまやかしの避難計画が作られ再稼働が進んでいるのである。
志賀町で震度7の地震が起こりで志賀原発が重大事故を起こしても「住民は安全に避難できる」とする訓練はこのようなまやかしの避難計画づくりの一環であり、志賀原発の再稼働を後押しするものでしかない。志賀原発の再稼働に不安を抱える多くの住民を巻き込むという意味でより悪質な再稼働戦略であり、本日も私たちは訓練反対を住民にアピールしてきた。
昨今、私たちは様々な自然災害に直面している。大地震や豪雨、豪雪だけでなく、クマが避難退域時検査場所近くに出没しても避難計画はストップする。原子力規制委員会・山中伸介委員長は原子力災害と自然災害が重なる複合災害では自然災害への対応優先と開き直り、被ばくを受け入れるよう求めている。詭弁を弄して原子力防災の破綻を認めない姿勢は許し難い。住民の命と暮らしを守るための最善の原子力防災は志賀原発の廃炉であることは明らかである。
2.能登半島地震の甚大な被害を無視した訓練
震度7を奥能登各地で観測した能登半島地震は、内陸地殻内地震としては国内最大規模であり、被害も過去に例を見ないものであった。多くの建物倒壊や道路の寸断、津波、土砂崩れ、液状化、大規模火災、広域かつ長期にわたる停電・断水・通信障害など、この30年間、日本が経験した大地震による被害が複層的に現れ、さらに海岸の隆起・沈降などの地殻変動も加わった。さらに原子力災害が重なっていたらどうなったか。志賀原発周辺住民だけではなく全国の原発立地地域の住民が、屋内退避も避難もできず、被ばくを強いられる恐怖を感じたのである。
一方、志賀原発との関係で能登半島地震を見るならば、立地自治体である志賀町北部で震度7を記録しつつも、原発敷地内の揺れは震度5強とされ、志賀町内の大きな被害は原発の北側(富来地区)に集中し、しかも奥能登地域のような壊滅的な被害には至らなかった。不幸中の幸いであった。しかし、志賀原発の沖合や半島陸域には次なる大地震を引き起こすことが懸念される大断層が数多く存在しており、政府地震調査委員会は今後30年以内に能登半島周辺でM7.0以上の地震が発生する確率を12~14%としている。次の幸運に期待はできない。
今回の訓練は、代替経路による避難や大型バスによる移動、防災業務関係者の参集状況などを見ても明らかなように、奥能登を襲った複合的、広域的、甚大、深刻な被害が志賀町やその周辺には起こらないだろうという極めて希望的、楽観的な想定下での訓練であり、原発震災の過小評価と言わざるをえない。
3.被ばくなしで避難できると誤解させる訓練
訓練の目的は「原子力災害時の緊急時対応に万全を期す」とされるが、「万全」とは何を意味するのか。多くの住民は計画通り避難すれば被ばくを回避できると受け止めるのではないか。しかし、県や市町の原子力防災計画や避難計画、そしてこれらの計画の根拠となる原子力災害対策指針を含め、計画の目的に「住民の被ばくを回避する」との文言は一言もない。政府は指針について「被ばくをゼロにすることを意図しているものではない」と明言し、原子力規制委員会は福島原発事故の100分の1の規模となるセシウム放出100TBqに相当する事故への備えとして、「めやす線量」を実効線量で100mSvの水準としている。一般公衆の年間線量限度の100倍という高い値である。当然ながら福島原発事故並みの事故となればさらに深刻な被ばくが想定される。さらにPAZ(原発から5km圏内)で孤立すれば100mSvを超える被ばくリスクすらありうることを認めている。また、先月3日の原子力災害対策指針の改定では、UPZの防護対策として被ばく低減効果が薄い屋内退避への依存度をさらに高めている。
この間、県や市町は被ばく前提の避難計画であることを認めようとしなかったが、今年1月に行った私たちとの交渉の場で、県は初めて国と同様、被ばくを前提とした計画であることを認めるに至った。
避難計画自体にこのような重大な欠陥があるにも関わらず、本日の訓練含め、この間の訓練を見る限り、避難住民や防災業務従事者の防護対策や避難退域時検査は年々簡略化されるなど、被ばくや汚染に対する意識を薄れさせる対応が加速している。馳知事が原子力防災に対する住民の理解促進を語るならば、まずは被ばく前提の計画であること、重大事故が起これば年間線量限度を大きく上回るリスクがあることを住民に正確に伝えるべきである。
2025年11月24日
志賀原発を廃炉に!訴訟原告団
さよなら!志賀原発ネットワーク
石川県平和運動センター
原水爆禁止石川県民会議
社会民主党石川県連合
石川県勤労者協議会連合会